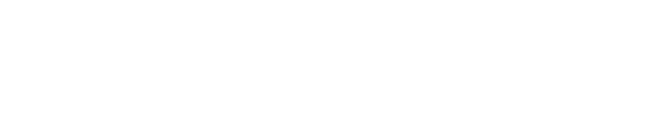令和7年 第2回 定例会
地域防災力向上について
東京都において、首都直下地震が今後30年以内に約70%の確率で発生すると予測されており、これに備えるためには耐震化や防災対策などの強化が不可欠です。昨年の第2回定例会一般質問では、防災訓練について、前回の総括質疑では災害関連死について質疑させていただきました。災害発生時の迅速な対応や被害の軽減を図るためには、地域防災力向上が極めて重要であると考えますので、今回はその視点で質疑させていただきます。
地域防災力向上には、区民や地域防災会による日頃の訓練が欠かせませんが、地域防災の中核を担う消防団の組織の活性化も不可欠だと考えます。本年1月1日現在消防団員数は定数500名に対し、396名であり、充足率は79.2%です。この充足率の向上は、地域防災力の強化にも直結すると考えます。昨年実施した消防団員へのアンケートによると約90%の団員が実動訓練の必要性を感じており、より実践的な訓練の実施や訓練の環境整備が求められます。現在、区役所旧庁舎では低層棟の取り壊しが完了し、今後は高層棟の取り壊しが予定されております。低層棟の取り壊し時には自衛隊による訓練が行われたと聞いておりますが、高層棟の取り壊しに際しては、消防団や地域防災会、関係団体が連携し、より実動的な防災訓練を実施することで、消防団員のモチベーション向上、地域防災会の防災力強化、連携強化にもつながると考えます。また、取り壊し後には以前行ったような、がれきでの救助犬訓練や、新たな試みとしてドローンを活用した訓練など、段階的な防災訓練の実施が出来ると考えますが、区の考えを伺います。
現在、中野サンプラザ再整備計画は頓挫しており、利活用や取り壊しの時期は未定ですが、順調に進めば今年9月頃には中野区の所有となる予定です。所有後は、中野サンプラザを活用した救助訓練の実施が可能となり、消防団や地域防災会、関係団体と連携して、実動訓練を行うことで、地域防災力の向上に寄与すると考えますが、区の考えを伺います。
また、区の計画では、小中学校施設整備計画をはじめ、老朽化した区有施設の建て替えを順次進める予定です。こうした区有施設の解体時に、消防団や地域防災会、関係団体と連携した実動訓練を標準化し、解体時に実施する枠組みを構築することで、防災啓発の機会を増やし、区民の防災意識向上にも寄与すると考えます。こうした仕組みの導入を検討してはどうかと考えますが、区の考えを伺います。
中野区では、地域ごとの【地域防災訓練】に加え、年二回の【中野区総合防災訓練】を実施しております。しかし、これらの訓練では認知症の方や障害のある方の参加が少なく、さらなる取り組みが求められます。中野区内には、認知症の方々が推定で10,000人以上、障害のある方々も10,000人以上おり、認知症の方々や障害のある方々にも訓練に参加していただくことで、災害時の対応力向上と地域の共助体制が強化されると考えます。防災訓練をより包括的かつ効果的なものとするため、関係団体との連携を強化することが、地域の防災力向上につながると考えますが、区の考えを伺います。
また、本年4月には中野区立の幼稚園、小学校、中学校合同の引き渡し訓練が実施されました。しかし、この訓練には、地域団体などの参加がなく、普段から通学時の安全確保に協力しているシルバー人材センターや地域団体などとも連携するべきではないかと考えます。学校と地域が協力することで、子ども達の安全確保や防災力向上にもつながると考えますが、区の考えを伺います。
縷々申し上げて参りましたが、地域ごとに環境が異なるため、全ての地域で同じ訓練を実施することは難しいと認識しております。しかしながら、各地域で行われた訓練から得られた知識や経験を共有することで、個人・地域・組織の防災力を向上させることが可能だと考えます。区が主体となり、地域間の情報共有を促進する枠組みを構築することで、より効果的な防災体制を築くことができると考えますが、区の考えを伺います。
中野区の広報について
中野区では、子育て支援や医療支援など、さまざまな福祉サービスを提供しています。しかし、必要な人に必要な時に情報が適切に届かなければ、区民が不利益を被るだけではなく、生活の質の低下にもつながります。
例えば、犯罪から区民を守り、地域の犯罪被害を防止するため、中野区では青色灯防犯パトロールカーを3台11名体制で運行しております。また、昨年の東京都知事選挙、東京都議会議員補欠選挙では、ラッピングした啓発宣伝カーを2台3日間運行し、区民意識・実態調査の結果によると、選挙の認知経路としてポスターや横断幕に次いで高い効果を示しました。医療啓発においては、乳がんの早期発見と治療の重要性を周知するため、ピンクリボン運動を実施し、庁有車50台に啓発マグネットシートを貼って運行しています。一方で、中野区では乳がん検診よりも検診率が低い他のがん検診に関する啓発カーの運行は行っていません。検診の頻度が増えれば、がんの早期発見、治療につながります。区では9月を【がん征圧月間】とされておりますので、他の事例に習い、この時期などに啓発カーの運行を行うべきと考えますが、区の考えを伺います。
次に児童館の広報について伺います。中野区内には18館の児童館があり、一部の施設ではすでに進めていますが、今後全ての児童館が基幹型児童館、乳幼児機能強化型児童館、中高生機能強化型児童館のいずれかに移行する予定です。また、今年度より大和児童館で、【ふらっとサンデー】が始まり、日曜日に利用できる児童館が増えることで、区民の交流が広がっています。しかし、児童館がそもそもどのような施設なのか、館内の様子やどの様な遊具があるかなど情報発信が十分ではなく、利用を促進するための工夫が必要だと考えます。例えば、公式HPで館内の様子を動画で紹介し、SNSにショート動画を掲載することで、児童館の魅力を分かりやすく伝えることができると考えますが、区の考えを伺います。また、乳幼児の保護者にとっては、児童館は有効な情報交換の場でもあります。先日、児童館を利用している保護者から、近隣の保育園や幼稚園などの情報が児童館にもっとあればよかったとの声をいただきました。こうしたニーズに応えるために、各児童館が関係機関との連携を強化し、利用者に適した情報発信を積極的に行うべきと考えますが、区の考えを伺います。
次に中野区の公式LINEについて伺います。公式LINEでは、さまざまな情報が配信されています。しかし、検索機能が弱いため、利用者が必要な情報にスムーズにアクセスしづらいと感じます。検索する際にはメニューから選択する必要があり、トーク画面で直接検索しても結果が表示されません。この仕様では、LINEで検索するメリットが十分に活かされていないと考えます。一方でHPでは新たにAIチャットボットシステムを導入しましたが、LINEの方にこそこうした機能を導入し、検索の利便性と精度を向上させることで、より多くの区民が情報に迅速にアクセスできるようになると考えますが、区の考えを伺います。
次に中野区の公式HPについて伺います。区の公式HPトップ画面には、【ナカペイ】や【引越しシーズンの役所窓口対応】など、さまざまな情報が掲載されています。しかし、掲載される情報や掲載期間に一貫性なく情報にも偏りがあるように思われます。区民に広報していく重要な情報であれば、今は【中野駅新北口駅前エリアのまちづくり】などの項目がありますが、現在はトップページに1つの情報しか掲載できない仕様となっています。他の自治体ではトップページをスライド形式にすることで複数の情報を掲載出来る様に工夫しており、中野区においても重要な情報の掲載基準を明確化し、区民に多様な情報を伝える仕組みを導入すべきと考えますが、区の考えを伺います。
また、特に重要な情報を区民に伝えるには、デジタルとアナログの両方を組み合わせた発信が効果的だと考えます。例えば、区報、区のHP、ナカノのナカニワなどで、情報発信の時期や内容に一貫性を持たせることで、より高い広報効果を得られると考えますが、区の考えを伺います。
先日、小学生の保護者からHPに掲載されている小中学校施設整備計画の資料が分かりづらいとの声をいただきました。現状では、委員会資料がそのまま掲載されており、区民にとっては分かりづらいと考えます。その他の資料についても同様であり、区長が目指す【つながる・はじまる・なかの】を実現するならば、行政資料を区民により分かりやすく伝える掲載方法を検討するべきと考えますが、区の考えを伺います。