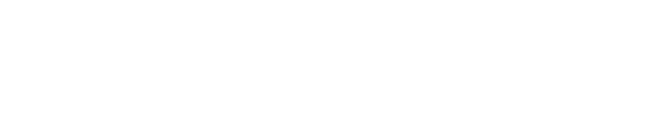令和7年 第3回 定例会
子どもの居場所について
中野区における子どもの居場所は、子育てひろば、児童館、学童クラブ、キッズ・プラザなど、多様な形態で展開されています。このうち子育てひろばは区内に8箇所設置され、多くの乳幼児親子にとって重要な居場所となっています。現行の整備方針は「乳幼児親子の徒歩圏内、おおむね半径500メートル圏域」とされていますが、実際には地域人口や利用実態との乖離が見られます。その結果、人口密集地域や利用需要の高い地域では「利用したくても利用できない」状況が生じ、一方で人口の少ない地域では稼働率の低下につながっています。こうした課題を踏まえ、現行の整備方針を基本としつつも、人口分布や地域特性、保育需要率などの要素を反映した、より実態に即した整備方針を導入すべきと考えますが、区の考えを伺います。
現行の徒歩圏内基準においては、特に区境部の地域で、近隣に子育てひろばが存在せず、利用が著しく困難なエリアが見受けられます。こうした地域的空白は、乳幼児親子にとって身近な居場所の確保が出来ず、子育て支援の公平性にも影響を及ぼします。他区では、地域ニーズを的確に捉えたうえで、出張型の【出張ひろば】や移動型の【移動型子育て支援車両】など、柔軟な形態による補完施策を展開し、空白地域の解消を図っています。中野区においても、現行の空白地域を補完する手段として、こうした出張型・移動型サービスを導入し、地域特性やニーズに即した形で空白地域を埋めていくべきと考えますが、区の考えを伺います。
中野区の子育てひろば事業は、18館すべての児童館でも実施されており、専用の子育てひろばと合わせて現在区内26箇所で展開されています。令和6年度の利用実績は延べ約190,000人に達し、曜日や時間帯によっては混雑して利用しづらかったと聞いています。その結果、暑い中せっかく来ても利用や相談ができない事態が生じています。さらに、乳幼児特有の感染症が流行する時期には、混雑する施設の利用控えが起こり、必要な支援機会の減少につながるおそれがあります。こうした状況を踏まえると、各施設のリアルタイム混雑状況が事前に把握できれば、利用者は混雑を避けて計画的に訪問でき、利用機会の確保や感染症リスクの低減にもつながります。他区では既に、乳幼児や児童が通う施設においてリアルタイム混雑表示を導入している事例があります。中野区においても、各施設の混雑状況や開催有無をスマートフォン等でリアルタイムで確認できる仕組みの導入を検討し、運営改善を図るべきと考えますが、区の考えを伺います。
現在、中野区内には子育て関連の居場所が多数ありますが、その案内は各施設の紙媒体やWeb情報にとどまっています。統合型GISを活用したオンラインマップも存在しますが、必要な情報に直接アクセスしづらく、利用者にとって分かりにくいのが現状です。このため、初めて利用する家庭や複数施設を比較検討する利用者にとっては、情報収集に時間と手間がかかり、利便性が十分に確保されているとは言えません。利用者の利便性向上を第一に考え、区内の子育て関連の居場所を一覧化した紙媒体の作成と、オンライン上で直感的かつ迅速に必要情報へアクセスできる情報提供システムの構築をするべきと考えますが、区の考えを伺います。
次に、施設の評価基準について伺います。子育てひろばを含む地域子育て支援拠点事業については、令和6年度の利用者アンケートで「地域とのつながりができた」と回答した割合が90%を超えるなど、一定の満足度が示されています。しかし現状では、施設ごとの評価指標が設定されていないため、例えば沼袋の子育てひろばで発生したような事態が再び起きた場合でも、契約を打ち切るかどうかを判断する明確な基準が存在しません。このままでは、事業改善や契約延長の可否を客観的に判断する仕組みが不十分なままとなります。そこで、各居場所の特色や運営状況を踏まえた評価指数を設定し、その結果を事業改善や契約締結の判断材料として活用するべきと考えますが、区の考えを伺います。
次に、学童クラブの地域偏在解消について伺います。現在、中野区内には区立学童クラブが24箇所、民間学童クラブが18箇所、合わせて42箇所設置されています。しかし、地域によっては依然として希望する学童クラブに入れない児童が発生し、通所に長距離移動を強いられるケースも見られます。こうした地域には、現在閉鎖管理中の区有施設や、活用可能な空き民間物件も存在しています。地域偏在を是正し、子どもの安全で身近な居場所を確保するためにも、これら既存施設などの有効活用を図るべきと考えますが、区の考えを伺います。
自殺対策について
令和7年6月11日に公布された改正自殺対策基本法では、子どもの自殺対策を基本理念に明記し、学校の責務を新たに規定するとともに、学校・教育委員会・児童相談所・精神保健福祉センター・医療機関・警察・民間団体等で構成する協議会の設置を可能としました。さらに、自殺未遂者や遺族への支援、心の健康保持に関する教育・啓発、医療提供体制や発生回避体制の整備など、施策の拡充が盛り込まれています。全国的には自殺者数は平成15年をピークに減少してきましたが、令和2年以降は新型コロナの影響や社会経済環境の変化を背景に、特に若年層と女性の自殺が増加傾向にあります。中野区でも同様に令和6年の自殺者は57名で、20代が最多、40歳未満が約半数を占め、女性も増加しており、全国的傾向と一致しています。区としてこの要因をどう把握・分析しているのか伺います。
自殺の要因は多岐にわたり、特に若年層や女性、精神疾患を抱える人は全国的にも自殺のハイリスク層とされています。令和6年の全国自殺者は、依然として若年層と女性の割合が高い状況です。また、自殺未遂者は再企図リスクが極めて高く、初動支援の遅れが命に直結することは多くの研究や自治体事例で明らかになっています。改正自殺対策基本法の趣旨を踏まえると、区単独での対応にとどまらず、救急搬送や医療機関受診が区境をまたぐケースが少なくない現状に即して、近隣区との情報共有・支援連携を制度化することが不可欠です。特に未遂者への迅速なアプローチと継続的な支援を実現するためには、医療・福祉・警察等を含む広域的な連携体制の構築が必要と考えますが、区の考えを伺います。
次にゲートキーパーについて伺います。中野区のゲートキーパー養成講座修了者は、これまでに累計約1,200人に達しています。しかし、近年の自殺増加傾向を踏まえると、養成者のさらなる拡充と活動の継続支援が求められています。 命を守るためには、養成した人材が継続的に学び、地域や学校で効果的に活動できるよう、研修や情報交換の機会を確保するとともに、関係機関との連携を強化することが不可欠です。 また、子どもの自殺予防には家庭の理解と関与も重要であり、教育委員会と連携して、保護者に対してもゲートキーパー養成講座の周知・参加促進を図るべきと考えますが、区の考えを伺います。
次にPFAについて伺います。災害時は生活環境の変化や孤立、喪失体験などによって自殺リスクが高まることが知られています。国際的には初期段階での心理的支援としてPFA(心理的応急処置)が標準的に用いられており、中野区においても、避難所運営マニュアル等に自殺リスク対応手順を明記し、職員や関係機関がPFAの考え方に基づく支援を行い、ハイリスク者を早期に支援につなげる仕組みを制度化すべきと考えますが、区の考えを伺います