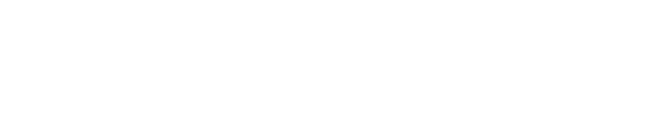令和7年 第1回 定例会
行動変容を促すナカペイの有効活用について
行動変容を促すナカペイの有効活用について伺います。
区は、来年度からナカペイと連動したコニュニティポイントを開始する予定です。このコニュニティポイントは、SWCの推進を図り、行動変容を促すことを主たる目的としておりますので、そういった視点で質疑させていただきます。昨年12月、我が会派と無所属議員の総勢14名で長野県長野市と上田市へ視察に伺いました。長野市では、モデル事業を経て、子どもの体験・学び応援事業として【みらいハッケンプロジェクト】を導入しております。この事業では、体験プログラムや教育サービスを受けるために3万円の電子ポイントを配布しております。子どもたちの体験・教育格差を解消するためには、保護者の収入に関わらず体験・教育の機会へ繋げることが重要であります。この長野市での事業では、ハンディキャップを持った子どもの新たな体験の場への繋がりや、不登校傾向の児童等のニーズに応える新たな手法にもなったとのことです。中野区もナカペイの裾野を広げることも見据えて、保護者の収入で子ども達にボーダーを引くことなく、民間事業者等が提供する体験・教育プログラムの利用に、コミュニティポイントを配布する方法について、区の考えを伺います
また、区民健診の受診率を向上させ、区民の健康に寄与することにも、コニュニティポイントは有効な手段と考えます。健診(検診)を受けた際にポイントを付与することも有効ですが、例えば、受診率の低い健診と受診率の高い健診を組み合わせて受診した場合、単体で受診するよりも多くのポイントを付与する方法や、特定の病気の危険因子に基づく健診(検診)を受けた場合により多くのポイントを付与するなど、複数の健診(検診)を受けた場合には、単体で健診(検診)を受けるよりも多くのポイントを付与する方法が効果的だと考えますが、区の考えを伺います
また、社会的孤立の防止や、様々な活動への参加を促進するために、ボランティア活動にポイントを付与することも有効だと考えます。例えば、認知症サポーター養成講座を受講し、その後にボランティア活動を行うことでポイントを付与する方法などが考えられます。この様なボランティア活動に対してポイントを付与する方法について、区の考えを伺いますナカペイの利用やコニュニティポイントの付与・利用データを収集・分析することで、区民同士や区民と行政を繋げる施策を打ち出すことが出来るのがこの事業のメリットだと考えます。今後はこれらの分析と施策展開はどこが行うか伺います。
認知症施策について
次に認知症施策について伺います
厚生労働省の推計では、令和4年の認知症と軽度認知障害の合計が1,000万人を超え、高齢者の約3.6人に1人が認知症又はその予備軍といえる状況にあるとされ、誰もが認知症になりえる時代となりました。政府は、そのような深刻な状況の中、昨年12月3日に【新しい認知症観】に立った【認知症施策推進基本計画】を閣議決定致しました。この新しい認知症観とは、認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。中野区では、令和4年よりもの忘れ検診を行っており、近隣区に比べて高い受診率になっております。認知症の疑いありと診断された場合は専門医を紹介され、認知症の疑いなしと言われた方にも検診時に通いの場マップが配布されます。この通いの場マップには、憩いの場として認知症地域支援推進事業やオレンジカフェが記載されておりますが、中野区でも推計18,000人以上の方が認知症又はその予備軍と考えると体制が十分とは思えません。例えば、認知症地域支援推進事業やオレンジカフェ、もの忘れ相談会に、他の分野の専門家も参加していただき、より多様な相談に対応できるようにしてはいかがでしょうか、区の考えを伺います。
また、区は【なかのオレンジカフェ事業】として後方支援を行っておりますが、新たな基本計画では推進体制として、行政職員が認知症の人や家族等と出会い知識や理解を深めることが重要であるとされています。これからは後方支援だけでなく、区職員自らが当事者やご家族と積極的な関わりを持つべきと考えますが、区の考えを伺います。
区では令和2年より認知症高齢者等個人賠償責任保険事業を始めております。認知症の方やご家族が安心できる事業ではありますが、現在の制度では18歳~39歳までの若年期認知症の方は対象外となっております。全ての認知症の方やご家族が安心できるよう、要綱を変更して、若年期認知症を含む全ての認知症の方を対象に入れるべきと考えますが、区の考えを伺います。福祉・介護サービス分野においても人手不足が想定されます。このままでは支援が届かない恐れがあります。区内には認知症サポーター・サポートリーダーが累計2万人以上おりますので、例えばアウトリーチチームと連携した支援体制を構築する等して行くべきと考えますが、区の考えを伺います。伺って次の項の質問に移ります。
ヤングケアラー・ケアラー支援施策について
次にヤングケアラー・ケアラー支援施策について伺います。
中野区は、令和5年10月より区内小学校4年生から6年生までの全児童及び区立中学校全生徒、ならびに区内在住の高校生世代に【ヤングケアラー実態調査】を実施しました。調査報告書によると、ヤングケアラーと思われる子どもは、小学生では国の調査結果と比べて高く、中学生ではほぼ同じ割合、高校生世代ではやや高いとの結果が示されました。ヤングケアラーの子ども達は、特に学校生活に影響が出ると思われますので、教育委員会はアンケート結果を受け、どの様な施策に繋げてきたか伺うと共に、教職員にヤングケアラーについての知識を深め、対応する研修等を行ってきたか伺います。
このアンケート調査を今回だけでなく、今後も定期的に様々な方法を用いて子ども達の状況把握に努めて行くべきだと考えます。例えば、子どもの意向を踏まえた状況把握を進めて行くために、面談の仕方などを工夫して確実に支援に繋げて行くような方法も考えられますが、区の考えを伺います。
子どもたちの中には、自分や友達がヤングケアラーであるのか、家庭での手伝いなのかを理解できていないケースが見受けられます。そのため、今後正確な状況把握を行うために、ヤングケアラーについて動画などを用いて指導を行うべきだと考えますが、区の考えを伺います。
また、元ヤングケアラーによる体験談等の講演や、児童生徒との交流会等も他の自治体では行っております。中野区でもこの様な取り組みを行い、児童生徒達により理解を深める取り組みをしてはどうかと考えますが、区の考えを伺います。
区長の施政方針演説内で、子どもの意見表明等の機会を広げるため、また、子どもや若者による意見表明と政策提言の推進を図るために、ハイティーン会議の対象年齢拡大、ハイティーン会議や若者会議の活動等を拡充すると言われましたが、不登校児童生徒や、ヤングケアラー達の意見表明等の機会や提言の場こそ設けるべきと考えますが、区の考えを伺います。
ハイティーン会議や若者会議では、その年代ならではの意見交換等がされておりますが、その中でヤングケアラーについての議論等はされてきたのか伺うと共に、同じ年代の子ども達がヤングケアラーについて主体的に物事を考え、意見表明していくことも必要だと考えますが、区の考えを伺います。
縷々申し上げて参りましたが、こうしている間もヤングケアラーやケアラー達は自らの健康や時間を削りながら介護を続けております。令和2年埼玉県でのケアラー支援条例を皮切りに、ケアラー達を包括的に支援して行くために多くの自治体で条例を制定しております。中野区でもヤングケアラーを含む【ケアラー支援条例】を制定していくべきと考えますが、区の考えを伺います。